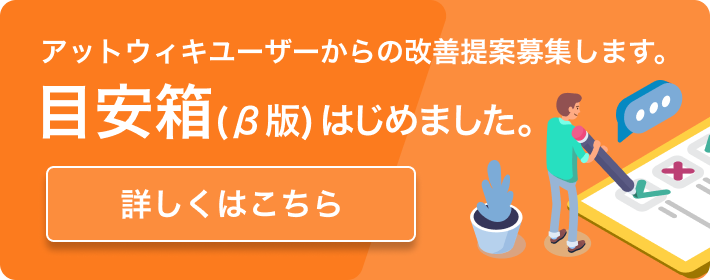lista de espera
1
最終更新:
bus
-
view
Al sur / 南へ向かうバスにのって(1)
「青春」と「童話」…『十九歳のジェイコブ』を読む (文: ウメハラコージ)
文庫本の帯には「胎内的な童話として再読されるべき中上最後の『19歳小説』は、永遠の乾き。」という菊池成孔の文章がある。そしてその右横には「すべての偉大なる作品は、青春文学なのだ。」という角川書店の宣伝文句がある。この一見何気ない配列で並んでいる二つの文章は、実に興味をそそるものである。
『十九歳のジェイコブ』は、1978年から79年に『焼けた眼、熱い喉』という表題で、角川書店の『野性時代』に連載された小説である。この雑誌の性格から言って、この小説は当初から「青春文学」というカテゴリーによって括られ、売られていたことがわかる。しかし、この作品から例えば村上龍の『69』のような爽快な「青春文学」を連想する者は、読んでみて愕然とし、熱さに耐えかねて本を放り出すに違いない。実際この作品は焼け焦げと暑さに満ちていて、異常に暑苦しいのだ。文庫版の解説を書いた斎藤環は、この作品の文章を「スピード感」と「濃密さ」というキーワードで片づけ、これを中上の作品全体に一般化しているが、少しそれは安易すぎるように思われる。他の中上作品と比べ、この作品の「スピード感」はほとんどないに等しく、また「濃密さ」はほとんど過剰なまでである。
『十九歳のジェイコブ』は、1978年から79年に『焼けた眼、熱い喉』という表題で、角川書店の『野性時代』に連載された小説である。この雑誌の性格から言って、この小説は当初から「青春文学」というカテゴリーによって括られ、売られていたことがわかる。しかし、この作品から例えば村上龍の『69』のような爽快な「青春文学」を連想する者は、読んでみて愕然とし、熱さに耐えかねて本を放り出すに違いない。実際この作品は焼け焦げと暑さに満ちていて、異常に暑苦しいのだ。文庫版の解説を書いた斎藤環は、この作品の文章を「スピード感」と「濃密さ」というキーワードで片づけ、これを中上の作品全体に一般化しているが、少しそれは安易すぎるように思われる。他の中上作品と比べ、この作品の「スピード感」はほとんどないに等しく、また「濃密さ」はほとんど過剰なまでである。
全集版の解説を担当したのは、野谷文昭である。野谷はこの作品について「この小説は揺れている。あるいは主人公の意識が絶えず揺らいでいるということなのか。犯行に結びつく動機が曖昧なのである」と正確に述べている。この作品を図式化すれば、『岬』『枯木灘』で描かれた「父殺し」のテーマが変奏されたものと言えるが、実はこの「父殺し」のテーマ(斎藤はこの作品のテーマをこの言葉で片づけているが、野谷はそうした単純な見解を取っていない)は限りなく希薄になっている。それには様々な理由があるが、最大の理由は野谷が指摘した通り、主人公ジェイコブの意識が終始グラグラと揺れ、さらに厚い透明な壁で覆われているためなのである。
この壁は、一読すればわかるように、ジャズとクスリで作られたものである。しかしその壁は、実は単に透明なものではない。何枚も厚いガラスを重ねると、その向こうに見えるものは歪み揺らいで見えるが、ジェイコブの眼は終始そうしたガラスの壁に取り囲まれている。このガラスを通すと、例えば凄惨な殺人のシーンもひどくリアリティを欠いたものになり(実はこの殺人はジェイコブの妄想かもしれないのだ)、クスリで酔っぱらっている喫茶店のシーンと変わらないものになってしまうのである。菊池が「胎内的」と言ったのはこのことであり、極めて正確な形容である。ジェイコブの世界は、かつて夢野久作が『ドグラ・マグラ』で描いた「胎児の夢」のごとく、動揺と非現実性に満ちているのだ。
この壁は、一読すればわかるように、ジャズとクスリで作られたものである。しかしその壁は、実は単に透明なものではない。何枚も厚いガラスを重ねると、その向こうに見えるものは歪み揺らいで見えるが、ジェイコブの眼は終始そうしたガラスの壁に取り囲まれている。このガラスを通すと、例えば凄惨な殺人のシーンもひどくリアリティを欠いたものになり(実はこの殺人はジェイコブの妄想かもしれないのだ)、クスリで酔っぱらっている喫茶店のシーンと変わらないものになってしまうのである。菊池が「胎内的」と言ったのはこのことであり、極めて正確な形容である。ジェイコブの世界は、かつて夢野久作が『ドグラ・マグラ』で描いた「胎児の夢」のごとく、動揺と非現実性に満ちているのだ。
そして、菊池のもう一つのキーワード「童話」を考えてみよう。童話が実は非常に残酷であることはいまや常識であるが、『十九歳のジェイコブ』はまさにそうした意味での「童話」にふさわしい。それは野谷が指摘した「動機の曖昧さ」につながってくるが、この作品では万事がすべて動機を欠き、そして安易に遂行されるのである。因果関係という言葉はこの作品では通用しない。その意味ではこれは坂口安吾が主張した、不条理と荒唐無稽に満ちた「ファルス」でもある。安吾はグリム童話をはじめとする多くの童話を「ファルス」と呼び、それをまさに文学の文学たるゆえんとして主張した。
この「ファルス」的な性質は、現代の「バーチャル」(これを先に指摘した「胎児の夢」として考えてほしい)で、「動物化するポストモダン」(東浩紀)の世界を生きる「若者」につきまとう病である。ジェイコブはこの意味で、まさにいまの「青春」を代表する存在である。その意味で、この作品はまさに「童話」であり、同時に「青春文学」なのである。
この「ファルス」的な性質は、現代の「バーチャル」(これを先に指摘した「胎児の夢」として考えてほしい)で、「動物化するポストモダン」(東浩紀)の世界を生きる「若者」につきまとう病である。ジェイコブはこの意味で、まさにいまの「青春」を代表する存在である。その意味で、この作品はまさに「童話」であり、同時に「青春文学」なのである。
その他ここで書き落とした数々のテーマがある。例えば「父殺し」のテーマ、初出の題名と登場人物の名前が変わっていること、「ジェイコブ」という名前に関わる寓意などであるが、ここでは割愛したい。それらは読者がこの作品を読み、さらに斎藤や野谷の解説を読みながら考えていただきたいことである。ただ、斎藤の解説は初心者には本当に役に立つが、筆者には少々中上を素直に読みすぎているような気がしてならないのだ。
中上健次の作品は、本当に意地悪く、そして読み応えのあるものである。
中上健次の作品は、本当に意地悪く、そして読み応えのあるものである。
『十九歳のジェイコブ』中上健次作
『中上健次全集』9(1996年)に収録(解説:野谷文昭)
2006年2月、角川文庫で復刊(解説:斎藤環)
『中上健次全集』9(1996年)に収録(解説:野谷文昭)
2006年2月、角川文庫で復刊(解説:斎藤環)