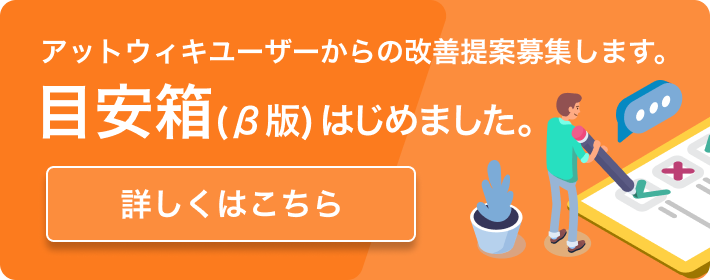Novel
神風1
最終更新:
匿名ユーザー
-
view
1(Epi.神風雛-I)
昭和18年、夏の暑い日のこと。
「ねえ、ちょっと!」
神風雛は、前を歩く恋人―――進藤拓馬を呼び止めた。
「…止まってよ!」
何度呼んでも聞こえないかのように前を歩き続ける拓馬に、痺れを切らした雛が腕をつかむ。
ようやく雛の顔を見た拓馬が、一言「何?」と言った。
ようやく雛の顔を見た拓馬が、一言「何?」と言った。
「…何?」
その言葉に、雛の頬が怒りでぐんと赤く染まる。
冷静な表情で、まるでいつもと変わらないように言葉をつむぐ拓馬が、雛には信じられなかった。
冷静な表情で、まるでいつもと変わらないように言葉をつむぐ拓馬が、雛には信じられなかった。
「何で「何」なんて言えるの?!」
「……」
「……」
雛の剣幕に黙り込む拓馬。その顔が、悲しそうにゆがむ。
それを見て、雛は黙るしかなかった。
それを見て、雛は黙るしかなかった。
本当はわかっていた。拓馬にはしゃべる言葉が見つからないということ。
でもなおさら、今だからこそ何か言い訳ぐらいして欲しかったのも事実だ。
でもなおさら、今だからこそ何か言い訳ぐらいして欲しかったのも事実だ。
「…なんで軍に志願したの?」
少しだけ躊躇って、雛は言った。
「…知りたいか?」
「知りたいよ」
「じゃあ言わない」
「……何よぉ」
「知りたいよ」
「じゃあ言わない」
「……何よぉ」
泣きそうだ。
こんな日くらい、いつもより優しくして欲しかった。発つのは明日なのだ。
抑えられていたいろんな感情が昂ぶり、それを拓馬に悟られたくなくて、下を向いた。
自然とつむじが拓馬に向けられる。
その向けられた頭を、拓馬はぽん、と撫でた。
抑えられていたいろんな感情が昂ぶり、それを拓馬に悟られたくなくて、下を向いた。
自然とつむじが拓馬に向けられる。
その向けられた頭を、拓馬はぽん、と撫でた。
「心配するな」
「…するわよ」
「…するわよ」
ふ、とため息をついたような音が聞こえた。
見上げると、拓馬は太陽のほうを向いていた。
もうすぐ夕時だ。山に入りかけの太陽は赤く眩しく、最後にふさわしいといえる突き抜けるような晴れた日。
思わず雛も同じ方向を向く。
真っ赤な太陽は戦火を逃れられず死んだ父の血のようで、
拓馬もこんな血を流して死んでしまうのではないか、と心配になり、思わず聞いた。
もうすぐ夕時だ。山に入りかけの太陽は赤く眩しく、最後にふさわしいといえる突き抜けるような晴れた日。
思わず雛も同じ方向を向く。
真っ赤な太陽は戦火を逃れられず死んだ父の血のようで、
拓馬もこんな血を流して死んでしまうのではないか、と心配になり、思わず聞いた。
「帰ってくる…?」
「帰ってくるよ」
「絶対よ」
「ああ、絶対だ」
「帰ってくるよ」
「絶対よ」
「ああ、絶対だ」
不安は消えなかった。
「私…聞いたの」
「何を?」
「何を?」
止まった足は歩き出すことなく、目的地の途中で履行することををやめた。
「神風特攻隊…って」
「ああ、俺が行くの空軍だもんな」
「ああ、俺が行くの空軍だもんな」
神風特攻隊。正確には神風特別攻撃隊と言う。
戦闘機ごと敵機に突撃する、一撃必死の攻撃をする隊のことで、それは隊員の死を意味していた。
また、海の特攻隊もあり、これは回天特攻隊という。
戦闘機ごと敵機に突撃する、一撃必死の攻撃をする隊のことで、それは隊員の死を意味していた。
また、海の特攻隊もあり、これは回天特攻隊という。
「私と同じ名前なんて…こんな不吉な名前!」
「大丈夫だよ。もし俺が…」
「言わないで!」
「大丈夫だよ。もし俺が…」
「言わないで!」
言いたいことがわかってしまって、雛は耳をふさぐ。
もし俺が神風特攻隊になったら…もしもでもそんな話は聞きたくなかった。
もし俺が神風特攻隊になったら…もしもでもそんな話は聞きたくなかった。
「聞けよ」
拓馬が優しく雛の耳をふさいだ両手をつかみ、下げる。
もっと触れて欲しいと願い、雛は涙を流した。最後だなんて信じたくなかった。
もっと触れて欲しいと願い、雛は涙を流した。最後だなんて信じたくなかった。
「もし俺が…特攻隊になっても。雛と同じ名前だ。雛に守られてるんだ」
「…っ…!」
「…っ…!」
息が詰まる。拓馬の顔を直視できず、ただただ下を向いて涙を流した。
雫は頬を伝って下に零れ落ち、地面へと溶ける。
雫は頬を伝って下に零れ落ち、地面へと溶ける。
「私、貴方を死なせるために守るんじゃない。貴方に生きて欲しい」
涙ながらにやっとそうつむいだ。
「わかってる。だから、戻ってくるよ」
「きっとね、絶対よ」
「ああ…」
「きっとね、絶対よ」
「ああ…」
ねぇ、約束…私は忘れなかったよ。
貴方からもらった手紙は、まだとってある。
今、もし貴方に会えたら…きっと言うね。
貴方からもらった手紙は、まだとってある。
今、もし貴方に会えたら…きっと言うね。
出会えてよかったって。